歯ぎしり・食いしばり
- 赤坂見附駅から徒歩1分の歯科医院「山王グランドビル歯科」
- 歯ぎしり・食いしばり
歯ぎしり・食いしばりとは?

歯ぎしりとは、睡眠中に上下の歯を強く噛み合わせ、横や前後にこすり合わせて「ギリギリ」と音を立てる動作を指します。一方、食いしばりは、歯を強く噛み締めたまま動かさずに力が加わっている状態をいいます。
これらの習慣が日常的に繰り返されると、歯だけでなく歯ぐきや歯を支える骨(歯槽骨)といった歯周組織、さらには顎関節や咀嚼筋にも負担がかかり、さまざまな不調を引き起こす原因となります。そのため、歯ぎしりや食いしばりは「悪習癖」とされ、口腔だけでなく全身の健康にも影響を及ぼすリスク因子とされています。
歯ぎしり・くいしばりは、次の2つに大別されます
- 睡眠時に起こるもの
- 起きている時に起こるもの
睡眠時の歯ぎしりは、音が出るため家族に指摘されて気づくことが多いですが、食いしばりは音が出ないため、自覚のない人も多く見られます。
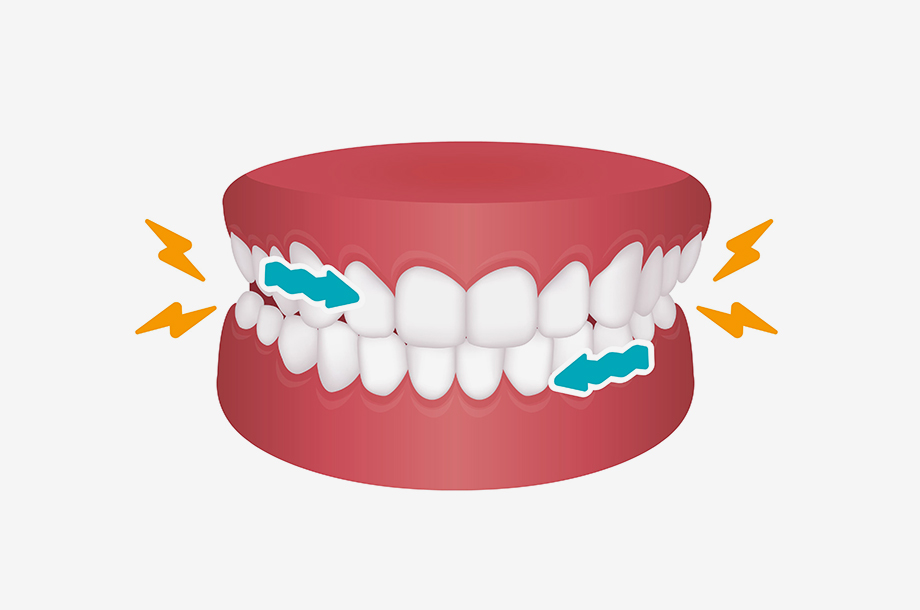
覚醒時には食いしばりが起こりやすく、緊張や集中している時などに、上下の歯が常に軽く接触したままになる歯列接触癖(TCH:Tooth Contacting Habit)という状態になることがあります。このような状態では、かかる力は弱くても長時間にわたって持続するため、歯や顎に負担をかけ、顎関節症の原因になることもあります。
歯ぎしり・食いしばりが与える影響
- 歯への影響:歯のすり減り(咬耗)、歯にヒビが入る、欠ける
- 詰め物・被せ物への影響:破折(割れ)や脱離(取れてしまう)
- 歯周組織への影響:歯ぐきや歯槽骨に過剰な負担がかかることで、歯周病の進行を助長
- 歯の神経への影響:神経に負担がかかることで、知覚過敏を引き起こす
- 筋肉への影響:咀嚼筋の過緊張による筋肉痛や緊張型頭痛の発症
- 顎関節への影響:顎関節およびその周囲の筋肉への過負荷により、顎関節症を発症
歯ぎしり・くいしばりのセルフチェックリスト
以下の項目に当てはまるものはありますか?複数当てはまる場合、歯ぎしりや食いしばりの影響が疑われます。
- 睡眠中に歯ぎしりをしていると家族などに指摘されたことがある
- 起床時や夕方に顎がだるい、または痛みを感じる
- 口を開けにくい、開けづらさを感じることがある
- 詰め物や被せ物がよく外れる
- 歯がすり減っていたり、欠けている箇所がある
- 冷たいものや熱いものがしみやすい(知覚過敏)
- 歯ぐきが下がって、歯が長く見える(歯肉の退縮)
- 舌や頬の内側に歯の跡がついている
- 歯の根元が削れているように見える
- 下の歯の内側や、上あごの中央にコブのような硬いふくらみがある(骨隆起)
歯ぎしり・食いしばりの治療
歯ぎしりや食いしばりの明確な原因はまだ解明されておらず、それ自体を完全になくすための根本的な治療法は確立されていません。そのため、特に就寝中の歯ぎしりや食いしばりに対しては、歯や歯ぐき、顎関節への負担を軽減するために、以下のような対症療法をご提案しています。
スプリント療法(マウスピース)
寝ている間にマウスピースを装着し、歯や顎にかかる力を分散・吸収します。
ボツリヌス療法(ボトックス注射)
咬筋などの咀嚼筋の緊張を緩和し、歯ぎしりやくいしばりの力を抑える効果が期待されます。
また、生活習慣の見直しやストレス管理など日常生活へのアドバイスを行い、顎関節症と診断された場合には、開口訓練(口を開ける運動)などのリハビリを併用することもあります。
スプリント療法のメリット・デメリット
メリット
- 睡眠中の咬合力や摩擦力を緩和し、歯・歯周組織・顎関節への負担を軽減します。
- 患者様ご自身で取り外しが可能で、不快感がある場合は外すこともできます。
- 噛み合わせの状態に応じて調整が可能です。
- 保険診療で作製可能なため、比較的負担が少なく治療を始められます。
デメリット
- ご自宅での就寝時の装着が必要となるため、使用しないと効果が得られません。
- いびきや睡眠時無呼吸症候群の症状を悪化させる可能性があります。
- 顎の位置が変化する恐れもあるため、使用中は定期的な歯科受診とチェックが必要です。
歯科医院で行うボツリヌス療法とは

歯ぎしりや食いしばりといった習慣的な強い咬み癖があると、咀嚼筋(噛むための筋肉)が過剰に緊張し、その働きすぎによってさまざまな不調が現れることがあります。こうした症状に対しては、筋肉の働きを一時的に抑え、力のコントロールを行うことで、歯や顎、口まわりの問題を改善する治療法があります。
この治療では、ボツリヌス菌が産生する「ボツリヌストキシン」と呼ばれるタンパク質製剤を、咀嚼筋などの対象となる筋肉に注入します。これにより筋肉の動きを一時的に緩め、症状の緩和を図ります。
歯科で行うボツリヌス療法は、美容目的の整形治療とは異なり、医師による適切な診査・診断のもと、医療行為として実施される治療です。
このような方におすすめ
- 顎が痛い
- 歯ぎしりや食いしばりがある
- 歯や詰め物がよく欠ける
- マウスピースの減りが早い
- 頭痛や肩こり、首のこりがある
- 口元の梅干しシワが気になる
当院のボツリヌス治療の特徴
当院では、歯科分野で広く使用されている「ボツラックス」という製剤を使用しています。主に咬筋に注射を行い、過剰な咬合力(噛む力)をやわらげることを目的としています。また、口元の筋肉の緊張が強く、いわゆる「梅干しジワ」ができやすい方には、顎先のオトガイ筋への注射も併せて行うことで、見た目の改善にもつながります。
歯科で行うボツリヌス療法のメリット
- 歯ぎしり・くいしばりの緩和
- 歯ぎしりやくいしばりで起こる、頭痛や肩こりの緩和
- 歯ぎしりやくいしばりによる知覚過敏や顎関節症状の緩和
- 歯の割れや欠け、マウスピース破損の緩和
- 発達した咬筋の弛緩(いわゆる小顔効果)
- 歯ぎしりが原因で進行する歯周病の緩和
- ガミースマイルの改善
- 口元の梅干しシワの改善
歯科で行うボツリヌス療法のデメリット
- 咬筋部の皮膚に注射を行うため、施術後に内出血や腫れが見られることがありますが、ほとんどの場合は数日以内に自然におさまります。
- 一時的に硬いものが噛みにくくなったり、顎に疲れを感じることがありますが、ボツリヌス製剤の効果が数か月で徐々に弱まるにつれて、自然に改善していきます。
- まれに、薬の効果が広範囲に及んだ場合、表情がややこわばるように感じることがありますが、これも薬効の消失とともに元に戻ります。
- ごくまれにアレルギー反応が起こる可能性も報告されていますので、気になる症状がある場合はすぐにご相談ください。
ボツリヌス療法の治療の流れ
①問診・触診・視診
症状によっては、施術前に歯科治療を必要とする場合もあります。
②施術
当該筋肉にボツリヌス製剤を注射します。数分で終わります。
当日の施術後の注意としては、
- 激しい運動はしない
- 長湯やサウナを控える
- 多量の飲酒をしない(晩酌程度でしたら問題ありません)
- 注射した部位を強く揉まない
上記のことに気をつけていただければ、直後からのお食事も全く問題ありません。
③1~2ヶ月後のチェック
効果が十分に出ているか、左右のバランスが取れているかなどを確認し、必要があれば追加で注射をします。
④半年〜1年後のチェック
状態を確認して、再治療が必要か検討します。患者様によっては、1回の治療で長期的に効果が出る場合もあります。
ボツリヌス療法の持続時間

ボツリヌス注射の効果は、通常2〜3日後から現れ始め、1〜2週間ほどで安定しピークに達します。その後は徐々に効果が薄れていき、個人差はありますが、おおよそ4〜6カ月ほどで効果がなくなります。効果を持続させたい場合は、3〜5カ月間隔での継続的な注射が推奨されます。ただし、効果は時間とともに自然に消失するため、万が一薬が効きすぎた場合でも、元の状態に戻るという安心感があります。
また、注射を継続することで、徐々に注射の間隔が長くなったり、最終的には注射が不要になるケースもあります。
そのため、「一生続けなければならない治療」というわけではありませんので、ご安心ください。




